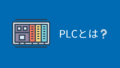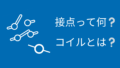【対象】初学者/実務者の基礎復習
【前提】先に「I/Oとは?」を読むと理解が早いです
【次に読む】「自己保持回路」「タイマー」「インターロック」
ラダー図とは
ラダー図とは、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)で使われる代表的なプログラム表現方法です。もともとはリレー回路の配線図を見やすくするために使われていた表記で、見た目がはしご(ladder)のように見えることから「ラダー」と呼ばれています。
ラダー図では、左側と右側に電源ラインを描き、その間に接点やコイルなどの記号を並べて回路を表現します。スイッチやセンサなどの「条件」を接点で表し、その条件がそろったときにランプやモータなどの「出力」をコイルでONさせる、というのが基本的な考え方です。
PLCでは、このラダー図を使って「どの入力信号が来たら、どの出力をONするか」をプログラムとして表現します。現場では、電気図面(ハード図)とラダー図を見比べながら、配線とラダーの動作をセットで理解していくことが多いです。
基本構造
ラダー図の見た目はいろいろありますが、基本となる構造はどのPLCメーカーでもほぼ共通です。まずは次の4つを押さえておくと、ラダー図の「骨格」がイメージしやすくなります。
- 左端と右端:電源ライン
左側がL側(+)、右側がN側(−)のイメージで、左から右へ電流が流れるような図になっています。この2本の縦線の間に接点やコイルを並べていきます。 - 横の線(段・ラング):1本ごとに1つの回路を表す
1本の横線を「1段(1ラング)」と呼びます。1段の中に、条件となる接点と、結果としてONさせたいコイルを書きます。 - 左側に接点、右側にコイル
ラダー図では、左側にスイッチやセンサを表す「接点」、右側にランプやソレノイド、内部リレーなどを表す「コイル」を配置します。左側の条件がそろうと、右側のコイルがONします。 - 上から下に順番に処理が実行される
PLCのCPUは、ラダー図を上から下、左から右の順番でスキャン(読み取り)し、各段の条件を評価します。この「スキャン」という考え方は、タイマーや自己保持を理解するうえでも重要なので、後半であらためて詳しく説明します。
この基本構造がわかってくると、ラダー図を見たときに「どこから電気が流れて、どこで止まっているのか」を追いかける感覚がつかめてきます。ただ、これは覚えることではなく勝手に身についていくものなので暗記するようなことではありません。
ラダーで使う基本要素
ラダー図を構成する基本的な部品は、大きく分けて「接点」と「コイル」です。
- 接点(A接点・B接点)
接点は、スイッチやセンサなどの入力信号をラダー上で表現する記号です。 - A接点(NO接点):通常はOFFで、スイッチやセンサの状態がONのときに導通する
- B接点(NC接点):通常はONで、スイッチやセンサの状態がOFFのときに導通する
- コイル
コイルは、ランプやモータ、ソレノイドなどの出力、または内部リレーやタイマーなどの「動作結果」を表す記号です。接点で作った条件が成立したときに、このコイルがONします。
👉 接点で条件を作り、コイルで出力や内部動作を指令するのがラダーの基本です。
A接点・B接点・コイルの詳しい動きや、図を使ったイメージは、別記事「A接点・B接点・コイルとは?」で解説しているので、記号ごとの挙動をしっかり理解したい方はそちらもあわせて読んでみてください。
直列・並列と論理(AND/OR)
ラダー図では、接点の並べ方によって「AND条件」「OR条件」を表現します。
- 直列に接点を並べる → AND条件
例:A接点①とA接点②を横一列に直列で並べると、「①がONかつ②がONのときにコイルがON」という条件になります。 - 並列に接点を並べる → OR条件
例:A接点①とA接点②を縦に分岐させて並べると、「①がONまたは②がONのときにコイルがON」という条件になります。
実際の制御では、
- 安全系のインターロック:AND条件が多い
- 手動/自動などの切り替え:OR条件になることが多い
といった使い分けをします。
ラダー図を読むときは、接点の記号そのものだけでなく、
- 直列でつながっているのか
- 途中で分岐して並列になっているのか
を意識すると、「この回路はどんな条件を満たしたときに動作するのか?」が理解しやすくなります。
簡単な例
「押しボタンスイッチでランプを点灯させる回路」をラダーで描くと、A接点(スイッチ)とコイル(ランプ)を横一列に並べた形になります。
見慣れない人でも電気回路図の延長として理解しやすいのが特徴です。
ラダーのスキャン動作
PLCは、ラダー図を一度だけ実行して終わりではなく、一定周期で繰り返しスキャンしています。ざっくりとした流れは次のとおりです。
- 入力の取り込み(入力リフレッシュ)
センサやスイッチなどのI/O入力の状態を、一度まとめてPLC内部に取り込みます。 - ラダーの実行
上から下、左から右の順にラダー図をスキャンし、各段の条件を評価してコイルのON/OFFを決めます。 - 出力の書き込み(出力リフレッシュ)
ラダー実行の結果をもとに、出力I/Oへ信号を出します。
このサイクルを数ms〜数十msといった周期で繰り返しているイメージです。自己保持回路やタイマー動作を理解するときには、
- 「1スキャンごとに評価されている」
- 「入力→処理→出力の順番で実行されている」
という前提を頭に置いておくと、ラダーの挙動をイメージしやすくなります。このラダーがスキャンされる順番というのは、ラダーを作成することにおける非常に重要な要素です。これは、また別記事で詳細な説明をする予定です。
ラダー図の特徴
- 直感的に理解できる:電気回路図に近い表現なので初心者でも学びやすい
- 現場で広く使われる:PLCエンジニアや保全担当者が最もよく扱うプログラム形式
- 資格試験でも必須:シーケンス制御検定や機械保全などの試験に必ず登場する
まとめ
ラダー図は、PLCを学ぶ上で最も基本となるプログラム表現方法です。
まずはA接点・B接点・コイルを理解し、押しボタンスイッチ回路や自己保持回路などの基本回路から学習するとスムーズにステップアップできます。
現場エンジニアの視点から見たラダー
ここまでの内容は、どちらかというと教科書的なラダー図の説明でした。最後に、現場でラダーを書いたり読むときに、僕が新人によく伝えているポイントをいくつか紹介します。
- まずはどのように動作するのが正解なのかをしっかり理解する。
- ラダーを読む人が読みやすく、意図を理解しやすいラダーにする。
- スキャンを意識し、スキャンごとの変化を意識する。
トラブル対応でも、いきなりラダーを漠然と眺めるのではなく、例えばボタンを押して、電磁弁が動作するはずが電磁弁が動作しないという時は、
- 入力ユニットでボタンの入力信号のアドレスランプが点灯しているか
- 出力ユニットで電磁弁の出力信号のアドレスランプが点灯しているか
というこの2点で、ラダーを見なくても判断できることがあります。入力信号のアドレスランプが点灯していないのであれば、入力ユニットにDC24Vが入力していないと言うことなので、ハードの問題である可能性が高いです。入力のランプが点灯していて、出力信号のランプが点灯していないのであれば、入力はしているがラダーで出力のコイルがオンしていないということなので基本ソフトの問題です。ハードの問題なのか、ソフトの問題なのかをまずは判断することが重要です。
また、ラダーを書くときは、
- 「この段は何をしたい段なのか(例:治具クランプ条件)」
- 「どの安全条件・インターロックを入れておかないと危ないか」
を日本語で一度文章にしてから、接点として並べていくと、後から見たときに理解しやすいラダーになります。コメントやシンボル名も含めて、「自分以外の人が読んでも意味が分かるラダー」を意識しておくと、後日ラダーを読む人も理解しやすくなります。
<執筆者の実務コメント>
工作機械メーカーで約20年。制御盤ハード設計/PLCラダー設計(主に三菱・FANUC)を担当。本記事はラダーの定義・基本構造と、A接点/B接点/コイルの要点を“簡単な例”と併せて押さえています。