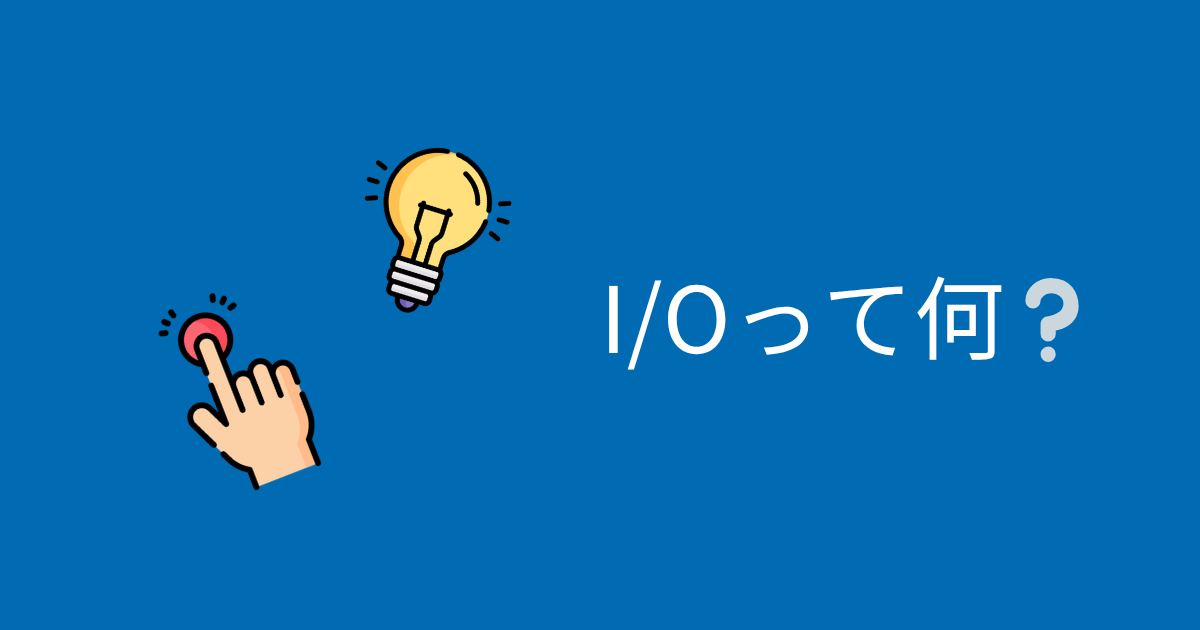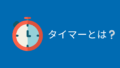【対象】初学者/実務者の基礎復習
【前提】先に「PLCとは?」を読むと全体像が掴めます
【次に読む】「A接点・B接点・コイル」「ラダーとは?」「自己保持回路」
はじめに
PLCやラダー図を学び始めると、必ず出てくるのが「I/O」という言葉。
「I/Oカード」や「I/O点数」など、よく聞くけど実は曖昧なまま使っている人も多いのではないでしょうか?
この記事では、I/Oの基本的な意味と、入力・出力の違いを初心者でもイメージしやすいように解説します。
I/Oとは?
I/Oは「Input / Output(インプット/アウトプット)」の略で、日本語では「入力」と「出力」を意味します。
- Input: スイッチやセンサなど、“PLCに情報を送る側”
- Output: PLCの信号を受けて、“動いたり光ったりする側”
入力(Input)の例
入力信号は、外の動きをPLCに伝える信号です。
代表的な入力機器
| 種類 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
| スイッチ | 押しボタンスイッチ、リミットスイッチ | ON/OFFで信号をPLCに送る |
| センサ | 近接スイッチ、フォトセンサ、圧力センサ | 物体や状態を検出して信号をPLCに送る |
入力がONになると、PLC内部の対応する入力端子(Xアドレス)がONとなり、ラダー図上で「信号が通る」状態になります。
デジタル入力とアナログ入力
PLCの入力は、大きく次の2種類に分けられます。
- デジタル入力
ON/OFFの2値だけを扱う入力です。押しボタンスイッチや近接センサ、リミットスイッチなど、「押した/押していない」「検出した/していない」といった情報をPLCに伝えます。 - アナログ入力
0〜10Vや4〜20mAなど、連続した値を扱う入力です。温度センサや圧力センサ、流量計など、「何℃か」「何MPaか」といった量をPLCに取り込みます。
本記事では主にデジタル入力を前提にしていますが、
「ON/OFFだけを見るのか」「値そのものを扱うのか」を意識しておくと、I/Oの全体像がつかみやすくなります。
出力(Output)の例
出力信号は、PLCが外部機器を動かすための信号です。
代表的な出力機器
| 種類 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
| ランプ | 動作中ランプ、異常ランプ | 状態を目で見えるように表示 |
| モータ | コンベア、ファン | 出力ONで動作開始 |
| ブザー | 警報、報知 | 出力ONでブザーを鳴らす |
出力信号がONになると、PLC内部の出力端子(Yアドレス)がONし、接続されたランプやモータが動作します。
デジタル出力とアナログ出力
出力も、入力と同じように2種類に分けて考えられます。
- デジタル出力
ランプを点ける/消す、モータを動かす/止める、といったON/OFFの制御に使います。
リレー出力・トランジスタ出力(ソース/シンク)など、方式によって接続できる相手が変わります。 - アナログ出力
インバータの速度指令や、バルブ開度の指令など、「0〜100%」のような連続量を出したいときに使います。
0〜10Vや4〜20mA信号で相手機器に指令を出すイメージです。
まずはデジタルから押さえれば十分ですが、将来的にインバータやサーボ、流量制御などに手を広げるときに、アナログ出力の存在も意識しておくとスムーズです。
PLC内部での流れ
I/O信号は、PLC内部で次のように処理されています。
- 入力(X)で外部の状態を読み取る
- PLC内部のラダー回路で論理処理(自己保持・インターロック等)
- 結果を出力(Y)に反映して外部機器を動かす
この流れが「入力 → 演算 → 出力」というPLC制御の基本サイクルです。
入力と出力の考え方
I/Oで混乱しがちなのが、「これは入力?出力?」という点です。迷ったときは、次のように考えると整理しやすくなります。
「誰が誰に情報を送っているか」を見る
- 人やセンサ → PLC に情報を送る
→ 入力(Input) - PLC → 機械や装置 に信号を送る
→ 出力(Output)
たとえば「ボタンを押してモータが動く」場合、
- スタートボタン … 人が押してPLCにON/OFFを伝えるので入力
- モータ … PLCからの信号を受けて動くので出力
となります。
「止めたいときにOFFにする側かどうか」を見る
- 止めたいときにOFFになるのが出力(モータ・ランプなど)
- 止める/動かす判断材料になるのが入力(センサ・スイッチなど)
と考えてもOKです。
I/Oカードとは?
I/Oカード(入出力ユニット/I/Oモジュール)とは、PLCと外部機器をつなぐための部品です。
スイッチやセンサなどの信号をPLCに取り込む「入力カード」と、PLCの出力信号でランプやモータなどを動かす「出力カード」に分かれています。
PLC本体(CPUユニット)はラダー回路の演算を行う頭脳の部分であり、実際の入出力端子は持っていません。
I/Oカードをベースユニット(ラック)に取り付けることで、PLCが外部機器と信号をやり取りできるようになります。
たとえば、入力カードがスイッチのON信号を検出し、その情報をPLCに送ります。
PLCはラダー回路を実行し、出力カードに信号を送り、モータやランプを動かす――この流れがPLC制御の基本です。
つまり、PLCが「頭脳」、I/Oカードが「手足」のような関係になっています。
I/Oカードを増設すれば、扱える信号点数(I/O点数)も増やせるため、より多くの機器を制御できます。
I/Oカードには、
- デジタル入力専用カード
- デジタル出力専用カード
- アナログ入力/出力カード
- 特殊I/O(位置決めユニット、安全I/O、シリアル通信など)
といった種類があり、必要な信号の種類や点数に応じて組み合わせて使います。
I/O点数とは?
「I/O点数」とは、PLCが扱える入力・出力の合計数のことです。
たとえば「入力16点・出力16点」であれば、最大で16個のスイッチ信号を受け取り、16個の機器を制御できるという意味になります。
エンジニア視点:I/O設計でよくある注意点
制御盤やPLCラダーを設計していると、I/Oまわりでは次のような点でトラブルになりやすいと感じています。
点数ギリギリで設計してあとから足りなくなる
「とりあえず今必要な分だけ」でI/O点数を決めてしまうと、仕様変更や機能追加のたびにすぐ足りなくなります。
- 予備I/O(入力・出力)を何点か確保しておく
- 将来の増設を見越して、ベースユニットや電源容量に余裕を持たせる
といった設計をしておくと、後から助かる場面が多いです。
I/Oの電圧・方式が合っていない
- NPN/PNP(シンク/ソース)の違い
- ACとDC の違い
- リレー出力/トランジスタ出力の違い
などを正しく理解していないと、「信号が入らない」「常にONになる」といった不具合が起きます。
I/Oの仕様は、必ずPLC・センサ・アクチュエータの取扱説明書をセットで確認し、「どの端子同士をつなぐのが正しいか」を図で整理しておくことが大切です。
まとめ
本記事では、I/Oの基本について次のポイントを整理しました。
- I/Oは「Input(入力)」と「Output(出力)」の略
- 入力は「外の状態をPLCに伝える信号」、出力は「PLCが機械を動かすための信号」
- 代表的な入力:スイッチ、各種センサなど(Xアドレス)
- 代表的な出力:モータ、ランプ、ブザーなど(Yアドレス)
- I/Oカードは、PLC本体と外部機器をつなぐ「手足」の役割を持つ
| 区分 | 主な機器 | アドレス例 |
|---|---|---|
| 入力(Input) | スイッチ、センサ | X000, X001… |
| 出力(Output) | モータ、ランプ | Y000, Y001… |
<執筆者の実務コメント>
工作機械メーカーで約20年。制御盤ハード設計/PLCラダー設計(主に三菱・FANUC)を担当。本記事は入力と出力の役割を分かりやすく解説し、学習の起点として実例をもとに信号の流れを整理しています。
▶ 次に読む:A接点・B接点・コイル/ラダーとは?/自己保持回路