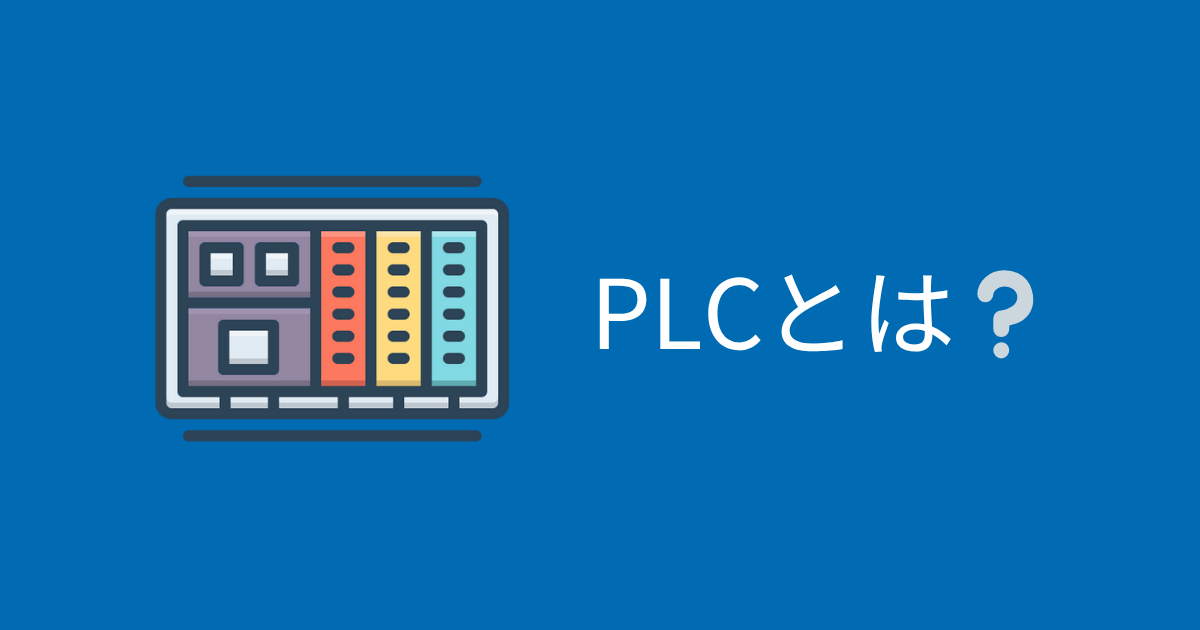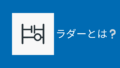【対象】初学者/実務者の基礎復習
【次に読む】「ラダーとは?」「A接点・B接点・コイル」「自己保持回路」
本記事では、PLC初心者が現場でつまずきやすい「PLCの仕組みと役割」を、
できるだけイメージしやすいように解説しています。
実際の制御盤設計や動作確認で使うポイント、現場での注意点も交えて説明します。
この記事でわかること
・PLCがどんな装置なのか(ざっくりイメージ)
・「入力→処理→出力」の基本的な動き
・PLCを構成する主なユニット(電源・CPU・入出力・通信)の役割
・リレー制御と比べたときのPLCのメリット
・三菱PLCとFANUC PMCの役割の違い
PLCとは何か
PLC(Programmable Logic Controller)は、工場や生産設備を自動で動かすための専用の制御機器です。見た目は小さな箱型のコンピュータのような装置で、中にプログラム(ラダー図)を書き込みます。
PLCはセンサやスイッチからの信号を受け取り(入力)、プログラムに従って判断(処理)し、その結果としてモーターやランプを動かす(出力)役割を果たします。
つまり、PLCは工場の頭脳として、自動化を実現する要の存在なのです。
PLCが活躍している代表的な設備
PLCは、工場の中の「いかにもロボットっぽい装置」だけでなく、意外と身近なところでも使われています。代表的な例をいくつか挙げると、次のような設備があります。
- 工作機械(マシニングセンタ、旋盤、研削盤 など)
- コンベアライン
- 自動倉庫・搬送装置(スタッカクレーン、パレタイザ など)
- 食品・飲料の充填機や包装ライン
- 自動車部品などの組立ライン
- ポンプ・ファンを使ったプラント設備(上下水処理、薬液供給 など)
これらの設備では、「センサで状態を検出 → PLCが条件を判断 → モータやシリンダを動かす」というサイクルがひたすら繰り返されています。工場見学などで動いている機械の裏側では、ほぼ必ずと言っていいほどPLCが仕事をしている、とイメージしてもらうとわかりやすいと思います。
工作機械メーカーの現場では、NCが軸制御や補間を担当し、
PLC(PMC)が周辺機器(クランプ、ドア、ポンプなど)のON/OFFや
安全インターロックを担当する、という役割分担が定番です。
PLCの仕組み(入力→処理→出力)
PLCの仕組みはとてもシンプルで、「入力」「処理」「出力」の3つの流れで成り立っています。
- 入力:スイッチやセンサが「オン/オフ」の信号を送る
- 処理:PLC内部のCPUがラダー図プログラムに従って判断する
- 出力:モーターを回す、ランプを点けるなど、機械を実際に動かす
例えば「スタートボタンを押す → PLCが信号を受け取る → コンベアモーターを回す」という流れです。
難しく考えず、「センサやボタンの情報を受けて、PLCが考えて、機械を動かす」と理解すればOKです。
PLCを構成する主なユニット
PLCは、実際にはいくつかの役割の違うユニットが組み合わさって1つのシステムとして動いています。メーカーや機種によって見た目や型番は違っても、基本的な構成要素はほとんど共通です。
- 電源ユニット
PLC全体に電源を供給する部分です。AC100VやAC200Vを受けて、PLC内部で使うDC電源に変換します。 - CPUユニット
いわゆる「頭脳」にあたる部分です。ラダーなどのユーザープログラムを実行し、入力の状態を読み取り、出力をON/OFFするかを判断します。内部メモリやタイマ、カウンタなどの管理もここで行われます。 - 入力ユニット(入力I/O)
スイッチやセンサからの信号を受け取る窓口です。スイッチやセンサからのDC24Vの信号を「ON」「OFF」としてCPUに伝えます。どの端子にどのセンサをつなぐかは、電気設計・制御設計で決めていく重要なポイントです。 - 出力ユニット(出力I/O)
ランプ、ソレノイド、リレー、モータの接触器などを動かすための信号を出す窓口です。CPUが「出力ON」と判断すると、このユニットから外部機器へ信号が出ます。入力ユニットではDC24Vを受け取っていたのに対し、出力ユニットではDC24Vを機器へ出力します。 - 通信ユニット(必要に応じて)
上位のPCやタッチパネル、他のPLC、インバータ、サーボアンプなどとデータをやり取りするためのユニットです。通信のインターフェースはEthernet、シリアル、フィールドネットワーク(CC-Link、PROFIBUS、PROFINETなど)など、用途に応じて使い分けます。
実務では、「どのI/Oに何をつなぐか」「どのネットワークでどの機器と通信するか」を最初にきちんと設計しておくことが大切です。
PLCでできること
PLCを使うと、例えばこんなメリットがあります。
- 自動化:ボタンひとつで設備が動く
- 安全制御:異常が起きたら機械を停止する
- 品質の安定:人による操作ムラを減らす
身近なところでは、エレベーターの制御や自動販売機の内部にも、PLCと同じ仕組みが使われています。
PLCとリレー制御の違い
PLCが普及する前は、リレーやタイマリレーだけで制御回路を組む「リレー制御」が一般的でした。今でも簡単な装置ではリレー制御が使われることがありますが、規模が大きくなるとほとんどの現場でPLCが使われています。
ざっくりまとめると、次のような違いがあります。
- リレー制御:配線で論理を作る(ハードだけで組む)
- PLC:ラダー(ソフト)で論理を作る(プログラムで組む)
リレー制御の特徴
- 接点リレーやタイマリレーをたくさん使い、配線で回路を構成する
- 条件を増やしたり変更したりするときは、配線のやり直しやリレーの追加が必要
- 回路図と盤内配線がそのまま1対1で対応するので、シンプルな装置ならわかりやすい
- 規模が大きくなるとリレー点数・配線量が膨大となるため、盤スペースや工数が厳しくなる
PLCの特徴
- 入出力信号はI/Oを経由してPLCに入り、内部ではラダーや命令語で論理を組む
- 条件変更はプログラムを書き換えるだけなので、仕様変更に柔軟に対応できる
- タイマやカウンタをいくつ追加しても、ラダーで作成するため物理的なリレーを増やす必要がない
- モニタ機能を使えば、「どの接点がONしていないか」「どこで処理が止まっているか」を画面で追えるので、調整やトラブル対応がしやすい
実務で感じる一番の違い
現場で一番効いてくるのは、「後から仕様が変わったとき」の対応のしやすさです。
試運転や量産立ち上げのタイミングでは、
- 「この条件を追加してほしい」
- 「動作タイミングを数秒遅らせたい」
- 「安全のためにもう1つインターロックを入れたい」
といった変更がよく発生します。
リレー制御だと、そのたびに配線の組み直しや部品追加が必要ですが、PLCならラダーを変更するだけで対応できます。
三菱PLCとFANUC PMC
三菱電機のPLCは、日本の工場で最もよく使われる汎用コントローラです。生産ラインや搬送装置など幅広い用途に対応でき、教材や資格試験でも三菱PLCが題材になることが多く、学習環境が整っています。
一方で、工作機械の分野ではFANUCのPMC(Programmable Machine Control)もよく使われます。PMCもラダー図で制御を行いますが、独立したPLCとは異なり、CNC装置に内蔵されている制御機能です。
つまり、PLCは独立した制御機器、PMCはCNC専用の内蔵制御機能。この違いを知っておくと、現場で混乱しにくくなります。
実務視点から見たPLC
ここまでの内容は、どちらかというと教科書的な説明でした。最後に、現場でPLCを使っているエンジニアの視点から、よく新人に伝えているポイントを少しだけ紹介します。
僕は工作機械メーカーで、電気調整や制御設計の仕事を約20年ほどやってきました。現場で新人や他部署の人にPLCを説明するときは、いきなり命令一覧やラダー記号の細かい話には入りません。まずは次の3つだけ意識してもらうようにしています。
- どこから信号が入ってくるか(入力)
- PLCの中でどう判断しているか(ラダー)
- どこへ信号が出ていくか(出力)
トラブル対応でも、この順番で追いかけるのが基本です。
- センサやスイッチの動きが、入力ユニットまでちゃんと入っているか
- 入力が入っている状態で、ラダー上の接点が想定どおりONになっているか
- ラダーの結果として出力コイルがONし、その信号が出力ユニットから機器へ出力されているか
慣れていない人ほど、ラダー画面だけをじっと見て悩んでしまいがちですが、実機では「入力ユニットのランプ(入力できていればランプが点灯) → ラダー → 実際の機器」という順番で確認するだけで、問題の切り分けがかなり楽になります。
また、PLCを学び始めたばかりの新人がよくつまずくのは、
- 「入力信号が来ていないのにラダーだけ見て悩む」
- 「NCとPLCの役割を理解せずごちゃごちゃになる」
- 「ラダーの処理を実際の機械の“動き”としてイメージできていない」
といったあたりです。
このブログでは、そういった「現場で新人がつまずきやすいポイント」を意識しながら、順番にPLCの考え方を整理していきます。「細かい命令を全部覚える」ことよりも、まずは 信号の流れと基本的な動き方 を掴むことを意識して読んでもらえると、実機に触ったときの理解がぐっと楽になるはずです。
まとめ
本記事では、PLCの全体像を次のポイントに分けて整理しました。
- PLCは、工場や生産設備を自動で動かすための専用制御機器であること
- 工作機械やコンベアライン、包装機、プラント設備など、さまざまな現場で使われていること
- 電源・CPUユニット・入出力ユニット・通信ユニットといった役割の違うユニットが組み合わさって1つのPLCシステムになっていること
- リレー制御と違い、「配線で論理を作る」のではなく、ラダー図などのプログラムで柔軟に制御できること
- 工作機械の世界では、三菱PLCとFANUC PMCがそれぞれ役割を分担して使われていること
細かい命令をすべて覚える必要はありませんが、
- どこから信号が入ってきて(入力)
- PLCの中でどう判断されて(処理)
- どこへ信号が出ていくのか(出力)
という「信号の流れ」をイメージできるようになると、PLCの動き方が一気につかみやすくなります。
<執筆者の実務コメント>
工作機械メーカーで約20年。制御盤ハード設計/PLCラダー設計(主に三菱・FANUC)を担当。本記事では、PLCの基本的な信号の流れ(入力→処理→出力)に加えて、実際の設備での使われ方や、リレー制御との違いを現場目線で整理しました。
▶ 次に読む:ラダーとは?/A接点・B接点・コイル/自己保持回路